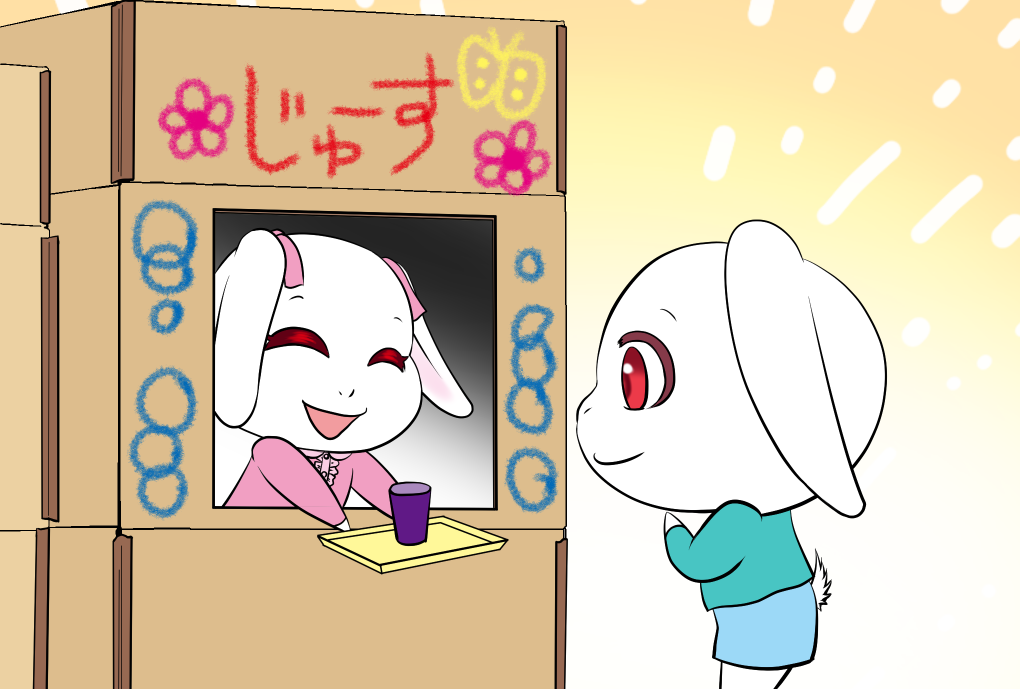大きな災害が起こると、電気・水道・ガスといったライフラインが高確率でストップします。復旧までに要する時間は2~3日、ひどい場合は一週間もかかります。
その間、皆さんはトイレを我慢できますか?
「トイレくらい……流せなくても適当にするからいいよ」と思われた方は、まだ大きな災害に遭われたことのない幸運な人でしょう。実際に大きな災害を経験した方は口をそろえて「簡易トイレを用意すればよかった」といいます。
先ほども申し上げたとおり、災害時にはライフラインの供給がストップするため、水が使えません。トイレも流せなくなりますし、トイレの水道管が壊れてしまっているケースも考えられます。そのような状態では、私たちはトイレの便器に用をたしていくという使い方しかできません。
日本はトイレがとてもきれいな国なので、便の臭いを嗅いだりすることは日常生活ではほとんどないでしょう。そのため、「トイレくらい~」と考えてしまいますが、換気扇もない状態で便を放置したときの臭いは想像を絶するくらいの悪臭なのです。実際に災害に遭われた方は、ビニール袋やトイレの便器に用をたして過ごしたそうですが、その悪臭はリビングに充満するほどだったといいます。
せっかく水や食料の備蓄をしているのに、「トイレに行きたくない」という理由で、食べたり飲んだりするのを我慢してしまうほど苦しい状況に陥ってしまうのです。
そこで、今回は、災害時に必ず備えたい非常用簡易トイレをご紹介したいと思います。しかし、どんな簡易トイレでもOKというわけではありません。中には絶対に選んではいけない簡易トイレもあるので注意が必要です。
携帯トイレじゃだめなの?
おすすめの簡易トイレは
自宅で被災したときのOK行為、NG行為
おわりに
〇携帯トイレじゃだめなの?
災害時に備えてトイレを購入するにあたり、100円ショップで済ませられないか?と思った人もいるのではないでしょうか。
実際、100円ショップにも携帯トイレが売られています。
セリアには3つ。ダイソーには2つ売られていました。
 使い方は、①ファスナーを開ける ②女性の場合は受け口を折り曲げて密着させる ③使用後はファスナーを閉める ④同封のビニール袋に入れて捨てる、となっています。
使い方は、①ファスナーを開ける ②女性の場合は受け口を折り曲げて密着させる ③使用後はファスナーを閉める ④同封のビニール袋に入れて捨てる、となっています。
どの袋もコンパクトな袋なので、皆、おしっこ用でした。パッケージに書いてある絵も、高速道路での車の渋滞向け、また、病人やけが人の介護用のイラストでした。
大便用には使えないという致命的なウィークポイントに加え、100均の商品は、材質もうーん……という感じです。
材質:容器、ポリウレタン・ポリエチレン・ポリプロピレン基材/高分子吸水材
このようにパッケージに書かれているのですが、これでは防菌効果はありません。
高分子吸収剤の説明を、JHPIA(日本衛星材料工業連合会)から以下、引用します。
『高分子吸水材は、高吸水性樹脂(Super Absorbent Polymer、略してSAP) と呼ばれ、1974年(昭和49年)に米国で開発されました。現在、日本で紙おむつに使用されている高分子吸水材はほんどがポリアクリル酸塩で、白色~淡黄色の無臭の粉末です(一社)日本衛生材料工業連合会に加盟しているメーカーの製品には、使用の有無を表示してあります) 。
高分子吸水材の最大の特長は吸水性と保水性です。脱脂綿やティシュー、パルプ等の吸水量が、自重の10~20倍程度なのに対して、高分子吸水材の場合は、純水で自重の200~1000倍、尿の場合でも30~70倍と、極めて高い吸水能力を持っています。また、高分子吸水材は、一度吸水した水分は、外から多少の圧力がかかってもほとんど放出しないなど、高い保水力も併せ持っています。
高分子吸水材の使用によって紙おむつの吸水保水性能が飛躍的に向上し、尿もれ・尿の肌への逆戻り等も大幅に改善されました。その結果、1日の使用枚数が少なくなったうえに、1枚あたりの紙・パルプの使用量も減って薄く軽くなり、紙おむつの軽量化、コンパクト化が実現しました』
つまり、高分子吸収剤は尿をすばやく吸水して固めるのに素晴らしい効果を発揮するものであって、単品では防臭性や防菌性はないものということが分かります。
災害時にはちょっとした病気も命とりなので、最低でも防菌効果のあるものを選びたいところです。
防菌タイプの凝固剤を使用することで、腸菌や黄色ブドウ球菌に感染するリスクをぐっと減らすことができます。下痢や腹痛といった症状はたいしたことのないように思えますが、体力の低下している災害時には治りにくくなっています。そのまま症状が進むと、腎不全や脳浮腫による意識障害やけいれんを引き起こすこともあるので注意が必要です。
また、避難所などの人の多いところで簡易トイレを使用する場合、臭いも気になるもの。より快適に用を足すためにも防臭タイプのものだとさらによいと思います。
実際、私は100均の携帯トイレをかたっぱしから使っていったのですが、中にはおしっこがうまく固まらず、タプタプ状態になってしまったものもありました。臭いはしませんでしたが、タプタプのおしっこは、「漏れるのではないか……?」とハラハラしました。
まとめると、選んではいけないトイレは以下のものです。
・防菌効果がないもの
・防臭効果がないもの
・ちゃんと固まらないもの
高速道路の走行中に子供が催したときのために……ということなら、防菌・防臭効果がなくとも、とりあえず車のシートにこぼさなければOKですが、災害時に使うものなら、周りの目や健康状態にかかわるので、しっかりと凝固剤を選びましょう。
〇おすすめの簡易トイレは
また、災害用簡易トイレは以下の項目をクリアしているものが望ましいです。
・持ち運びが簡単かどうか
・丈夫かどうか(使っている間に壊れないか)
・災害状況が終息したときに簡単に処分できるか
丈夫というのはもちろんのこと、やはり『トイレ』は汚物を入れるものなので、災害が収束したら捨てるのが衛生的です。次の災害用にまた洗って長期保存しておく……というのはちょっと気になります。
プラスチック製の簡易トイレも売られていますが、農作業用や介護用などで毎日使うわけではないのであれば、どこに収納しておくか頭を悩ませてしまいます。
そんなときには、『災害時にのみ使えるダンボール製の簡易トイレ』が便利です。
 ダンボール製品というと、「すぐに壊れちゃいそう」「ちゃっちそう」と思われるかもしれませんが、大人が1週間使ってもまったく問題ありません。災害時の対策として、ひとつ携帯式の簡易トイレを購入しておくと安心だと思います。
ダンボール製品というと、「すぐに壊れちゃいそう」「ちゃっちそう」と思われるかもしれませんが、大人が1週間使ってもまったく問題ありません。災害時の対策として、ひとつ携帯式の簡易トイレを購入しておくと安心だと思います。
災害用トイレとしておすすめなのは、『たすけくん』という簡易トイレです。
こちらは浜松市、磐田市の各自治会や県立高校の災害備品として購入されている簡易トイレで、ダンボール製の組み立て式です。
組み立てる前は、高さ310㎜、幅280㎜、奥行き400㎜の長方形の箱になっており、持ち運びやすいように取っ手がついています。重さも女性が片手で持てる重さとなっています。大きすぎないので車に常に積んでおくのも良いと思います。
組み立てれば、200㎏もの重さに耐えるので、お父さんでも安心して使えますし、丈夫なので家族で何度も使うことができます。
価格は6回分の消耗品(処理用袋、消臭凝固剤)がついて2,160円。
避難所などの人の目があるところでトイレをする場合に備えて、目隠し用のコートも売られています。すっぽりかぶれば、外からは簡易トイレが見えなくなるので、安心して用を足すことができそうです。こちらの目隠し用コートは2,000円となっています。
「6回セットだけじゃ不安……」という方の声を反映し、『たすけくん』には消耗品だけのキットも売られています(処理用ポリ袋×10袋、消臭凝固剤×10袋、ポケットティッシュ10個で1,000円)。
トイレの凝固剤は、価格もバラバラで成分もバラバラです。
ただ便を固めるだけのものもありますし、防臭効果や防菌効果のあるものもあります。
数時間のおでかけの際に使う時ならばどんな凝固剤を使用してもかまわないと思いますが、災害時には、ちょっとした病気も命とりなので、最低でも防菌効果のあるものを選びましょう。
これにより、腸菌や黄色ブドウ球菌に感染するリスクをぐっと減らすことができます。下痢や腹痛といった症状はたいしたことのないように思えますが、体力の低下している災害時には治りにくくなっています。そのまま症状が進むと、腎不全や脳浮腫による意識障害やけいれんを引き起こすこともあるので注意が必要です。
また、避難所などの人の多いところで簡易トイレを使用する場合、臭いも気になるもの。『たすけくん』
についている凝固剤なら、消臭・防菌効果のあるものなので安心です。
安すぎるポリ袋を使うと、最悪の場合、やぶける可能性もあるので、袋もできれば『汚物用』に使えるものを使いたいですよね。備えあれば患いなし。3点セットで1,000円なので、いざというときのために買っておくと心強いです。
〇自宅で被災したときのOK行為、NG行為
自宅で被災したとき、私たちはどうしたらいいのでしょうか。とるべき行動や、絶対にNGな行動をまとめてみたいと思います。
・まずは身の安全を図る
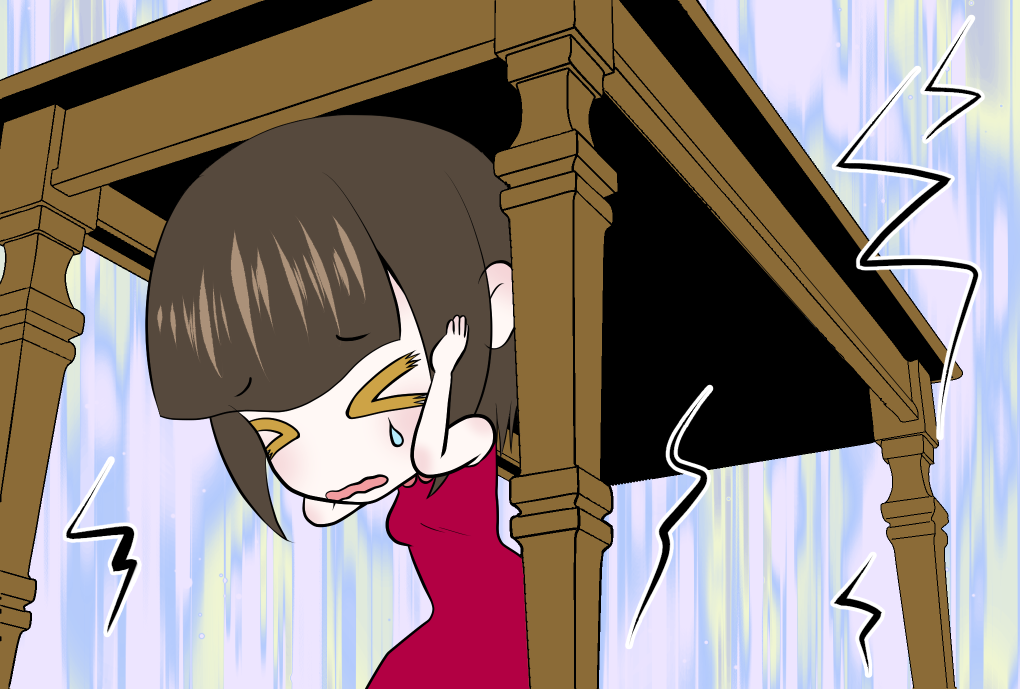 誰もが小学生の時、避難訓練を経験したと思います。地震の発生直後は、あの避難訓練のようにまずは机の下などに隠れ、身を守ります。とくに頭になにかが落ちてくると重症になりやすいので、頭を守りましょう。もし、火を使っている場合はすぐに消します。阪神淡路大震災のときは、通電火災により火災が広がりました。
誰もが小学生の時、避難訓練を経験したと思います。地震の発生直後は、あの避難訓練のようにまずは机の下などに隠れ、身を守ります。とくに頭になにかが落ちてくると重症になりやすいので、頭を守りましょう。もし、火を使っている場合はすぐに消します。阪神淡路大震災のときは、通電火災により火災が広がりました。
通電火災とは……地震による停電から復旧した際に、停電前まで使っていて、スイッチがオンになったままの電熱製品が出火して引き起こされる火災のことです。電気コードの破損や、白熱灯・電気スタンド・電気ストーブ・オーブントースターなどが通電したことによって、落下物などに引火して火災を引き起こします。1995年の阪神・淡路大震災では、神戸市で発生した建物火災157件のうち、35件が電気火災でした。2011年の東日本大震災では、本震による火災全111件のうち、約54%が電気関係による火災でした(マンションラボより https://www.mlab.ne.jp/safety/columns_20190716/)』。
・すぐに外に飛び出さない
「大きな地震が起こった時には、安全な屋外に飛び出そう」――そう思っている人も多いのですが、これはかえって危険です。地震で家の塀やビルの窓ガラスが落ちてくる可能性があるからです。
揺れが収まるまで、じっと机の下で身の安全をはかりましょう。
お風呂にいた場合……ドアがゆがまないように出入り口を開けます。そして、お風呂に入り、浴槽のフタをしましょう。地震によって鏡が割れることもあるので地震後は足元に注意しましょう。お風呂に入っていた場合、はやく服を着ようと慌ててしまいますが、まずは安全確保を優先させてください。
トイレにいた場合……まずは出入り口のドアを開けて避難経路を確保します。出入り口を開けたら、すぐに飛び出すのはNG。揺れが収まるまでは低い姿勢でトイレの中で頭部を守ってじっとしていましょう。トイレに鏡がある場合は、割れる危険性があるので出たほうが良い場合もあります。
台所にいた場合……料理を作っていた場合は、すぐにやめましょう。揺れが大きい場合は、火を消すよりもさきに逃げてください。台所には包丁や火など、危ないものがたくさんあるので、すぐに避難します。
・家族の安全を確保して身の回りを確認
家族の身の安全を確保し、火が出ないか確認したら、飛び散ったガラスや転倒した家具に注意しながらガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切って避難します。
もし、地震による津波の恐れがある場合は、一刻の猶予もないので、避難準備よりも避難所への移動を優先させてください。
・避難所へは徒歩で
避難するときには徒歩が安全です。車での避難の場合、渋滞に巻き込まれたり、緊急車両の妨げになってしまいます。また、停電で信号が消えているので帰って危ないのです。
倒壊しそうな家屋のそばは慎重に通過しましょう。
【絶対にしてはいけないこと】
・今にも壊れそうな家屋で貴重品を探す行為
・一人で他の人を救助する行為
・裸足で歩く行為
・車で逃げる行為
・災害直後に離れた場所にいる家族を探しに行く行為
〇おわりに
被災したときにどう動くか。そして貯えがあるかどうかでその後の生活がまったく違います。家族の安全を守るためにも、しっかりと知識を持って、対処しましょう。